 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
冬の馬
初出:『テアトロ』1993年1月号 p146~194
収録:「清水邦夫全仕事 1992~2000」p7~73 河出書房新社 2000.6.23

【上演データ】
1992(平4)年12月10日~25日
木冬社第18回公演、木冬社=シアターX(カイ)提携公演
会場:シアターX(カイ)
演出:清水邦夫
美術:朝倉攝
照明:服部基
音響:深川定次
舞台監督:堀井俊和
制作:倉掛淳一
出演:米倉斉加年(吉村研一)/松本典子(吉村波子)/磯部勉(村上通)/黒木里美(中島美枝)/中村美代子/南谷朝子/玉城美〓/菊岡薫/林香子/越前屋加代/田中幹子/石塚智二/松戸賢一/他
【あらすじ】
東京近郊のとある町にある吉村時計修理店。今は時計の修理はせず、大正時代の手作りの銀時計を作っている。ここの女主人・波子はかつて夫も子供もいながら、同じように妻子ある大学教授とかけおちして、この時計屋を始めたのだ。その夫も亡くなり、今は、前夫とともに捨てた実の息子・通の別れた妻・美枝と二人で暮らしている。
ある日、死んだ夫の息子、つまり義理の息子・研一が訪ねてくる。波子と研一は同じ歳で、ずっと以前病気になった時に四ヶ月ほど一緒に暮らしただけの間柄である。夫が死んだとき、この家の処分は5年後に決めようと言ったきり、7年間連絡がなかったのだが、突然やって来たのだ。妻や娘と一緒にマンションで暮らしている筈なのだが、「自分の住む場所が欲しい」という研一には何か事情がありそうだ…。
【コメント】
「弟よ」「哄笑」に続き“愛のかたち”三部作の最終篇と銘打たれて上演されました。いよいよ血の繋がらない同じ歳の母と息子の登場です。何がいよいよかと言うと、以前やはり血の繋がらない母と息子が登場した作品がありましたが、この時は年齢がちょっと離れすぎてロマンスというわけにはいかなかったからです。わざわざ米倉斉加年を連れて来た、ということは…
「冬の馬」とは次のような逸話に基づくものです。太平洋戦争末期、軍用馬の産地・木曾では次々と馬が徴用され、ついに一頭もいなくなってしまった。馬のいない生活に張りや支えを失った人々は無気力になり、喧嘩や殴り合いばかり。冬になると更に事態は悪化し、誰もが駄目になっていった。その時、空になった馬小屋に馬がいることにしたらどうだろう、と言い出す者がいた。すると人々は皆嬉々として幻の馬の世話をしはじめ、生活のリズムを取り戻した。
つまり、すでにいないものを「いる」と思うことで生活に張りを出し、人間の尊厳を取り戻そうとする、夫に死なれても何とか背筋を伸ばして生きようとする主人公の考えた遊びです。
ところで、この公演はシアターX(カイ)で上演されましたが、実は「シアター目白館」という劇場で上演されるはずでした。木冬社のアトリエも兼ねた劇場として建設中だったのですが、突然出資者が手を引いたのです。これは紛れもなくバブルの崩壊によるものでした。楽しみにしていたので非常に残念でした。まさに「幻の劇場」となってしまったのでした。


|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright (c)1998-2023 Yuko Nagai All Rights Reserved. |
|
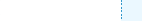
|
|
 |