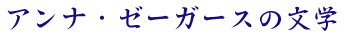Die Toten bleiben jung, 1949
死者はいつまでも若い


北通文,道家忠道,山下肇,新村浩訳 白水社 〔上〕1953.3.10 280円 〔下〕1953.3.30 300円
読み始めてすぐ、これはアンナ・ゼーガースの「戦争と平和」なんだな、と思った。様々な階級のそれぞれの人生を複合的に描いて戦争を描くという、あの形式。1919年~1945年、第一次大戦終了後から第二次大戦終結までのドイツを舞台に五つの家族とその周囲の人々がほぼ二世代にわたって描かれている。
スパルタクス団のエルヴィンを射殺するところで物語は始まる。このエルヴィンにかかわった人々がそれぞれの物語を展開する。
- 支配階級側
- クレム - 新興の資本家。除隊後樹脂工場を経営。
- リーヴェン - バルト海地方の旧家だが没落して領地を失った。銀行家。ニヒリストで享楽家で冒険心から早い時期にナチに入党する。
- ヴェンツロー - プロイセンの旧家出身の軍人。国防軍に入隊。
- リーヴェン - バルト海地方の旧家だが没落して領地を失った。銀行家。ニヒリストで享楽家で冒険心から早い時期にナチに入党する。
- 被支配階級側
- ナードラー - 農民
- ゲシュケ - 労働者
このうち、クレム、リーヴェン、ヴェンツロー、ナードラーがエルヴィンを射殺した側で、ゲシュケはエルヴィンの子供を産んだマリーを子供ごと引き取った労働者である。
まずは新興資本家の後押しをもってナチが政権を得ることができた、その背景がクルツ一家によって描かれる。クルツの息子が最後にはナチの凶暴で残酷な将校となって現れる。また、クルツには戦友で銃卒のベッカーが常にそばについていて、復員後も運転手として、忠信をもって使えている。自分では深い友情でもってクルツと結ばれているつもりでいるが、同じ新興資本家の妻をもらうために、ベッカーを解雇しようとする。これが原因でこの二人は無理心中のような形で比較的早い段階で物語から姿を消す。ここに「越えられない階級」が描かれている。
ナチのバックにあったのが、プロイセンの軍国主義であったことは歴史的な事実である。ヴェンツローは凡庸ではあるが軍務に忠実な軍人で、一家の周囲には旧プロイセンのにおいが漂う人物が多々登場する。ヴェンツローの叔母アマーリエは頑固なドイツの婆さんという感じだが、誰よりも賢い女性に見える。
リーヴェンの中にニーチェのニヒリズムをただよわすことに作者は成功している。登場人物としては最も楽しい人物なのだが、やはり最後は悲劇的な結末を皮肉っぽく迎える。
ナードラーによって、支配欲、権力欲におそわれた農民が何故ナチに惹かれたのか、がよくわかる。が、結局戦死するだけであまり重要な人物とは言い難い。この一家は家族の方が面白い。妻のリーゼはタフな農家のおかみさんだし、弟のクリスティアンは負傷して片足しかなく、現実と接触を極力減らし、世間の片隅で靴を修繕して暮らしているが、なかなかどうして、したたかな人物である。この二人の子供であるカールがソ連の捕虜となったところで、この一家の登場は幕を閉じる。
だが、この物語の主人公といってよいのはエルヴィンの子供を産んだマリーと息子のハンスである。その血を引いたのか、反骨精神の高い青年に育つ。ハンスの養父ゲシュケによってワイマール時代の社会民主党と共産党の分裂、労働者の連帯が不足した理由などがよくわかる仕組みになっている。
ほかに、ヴェンツローの長女アンネリーゼに多少ゼーガース自身の面影が見える。
この作品では作者は極力ナチのユダヤ人狩りなど悲惨な情景は必要最低限に押さえ、普通の人々が何故ナチへ惹かれていったか、それを解明することによって戦後の精神的なダメージを大きく受けたドイツの青少年の精神の復興を目指したものと思われる。非常にパースペクティブな大作で、夢中で読んだ。ただ、あまりにも古い本で読みづらかったのが難点。どうして1953年(昭和28年!)以降の版がないのだろう?
 Die Toten bleiben jung, 1968
Die Toten bleiben jung, 1968
Directed by Joachim Kunert
Cast: Kurt Bowe, Barbara Dittus, Michael Gwisdek
Country: East Germany
2001.10.25