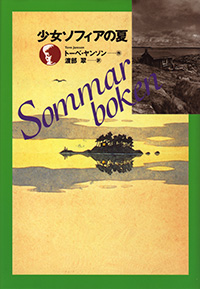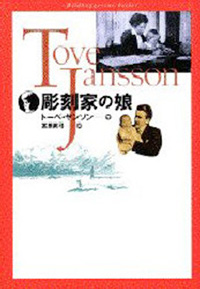日本で未訳の海外作品を105冊紹介するブックガイド。"これはおもしろそう、読みたい"と思っても、すぐには絶対に読めないというストレスの貯まりそうな本だなぁと思いつつ、好奇心には勝てず、つい買ってしまった。ひょっとして、うまくいけばいずれ読めるかも、でもだいたいは読めないと思って間違いないわけで、やはりちょっと悔しいものがある。
日本で未訳の海外作品を105冊紹介するブックガイド。"これはおもしろそう、読みたい"と思っても、すぐには絶対に読めないというストレスの貯まりそうな本だなぁと思いつつ、好奇心には勝てず、つい買ってしまった。ひょっとして、うまくいけばいずれ読めるかも、でもだいたいは読めないと思って間違いないわけで、やはりちょっと悔しいものがある。
まず、この本を読んで驚いたのは、これだけの数の言語・文学を研究する研究者・翻訳者が日本にいるということだ。自治領含め63カ国、関わった83人のうち、50人から先はSNSでひっぱってきたそうだ。本当によくこんなにたくさんの国について研究している人がいると感嘆する。素晴らしい。あの沈みそうで有名なツバルまで入っているとは。グアドループという国名(自治領)を私は初めて知った。
本書は確かにブックガイドなのだが、最近の作品が多く取り上げられているので、いま世界の国々で人々がどんなことを考えているのか、どんな様子なのかが少しずつわかるような本に仕上がっていて、一通り読むだけで楽しめる。
●まず、やっぱりこの辺が読みたい5冊。
キューバのレオナルド・パドゥーラ「犬が好きだった男」。トロツキーが亡命先のメキシコで暗殺された事件を取り扱った小説。キューバとトロツキーと言えば、亡命中のフリーダ・カーロとの短い関係を思い起こす。この作品は暗殺者の方に焦点が当てられているようで、おもしろそうだ。翻訳されている「アディオス、ヘミングウェイ」から考えるとミステリー小説のような作品かもしれない。パドゥーラと言えば脚本を担当した映画「セブン・デイズ・イン・ハバナ」も観なくては。
プエルト・リコのエドゥアルド・ラロ「シモーヌ」。ボラーニョも受賞したロムロ・ガジェゴス賞を2013年に受賞した作品だそうなので、これも気になる。ジュノ・ディアスやダニエル・アラルコンとは違うようだが。
ペルーのサンティアゴ・ロンカリオーロ「赤い四月」は連続殺人を扱かったサイコ・スリラーだが、地方都市アヤクーチョの様子がわかる小説なんて、巡り会うことはなかなかないので、読んでみたい。
ボリビアのエドムンド・パス=ソルダン「北」はアメリカに渡ったラティーノたちの三つのストーリーが並行して進むそうだが、後半は実在の連続殺人犯をモデルとした登場人物の話。この辺が気になってしまうのは、どうしたって「2666」の影響だろうと思う。
アルゼンチンのメンポ・ジャルディネッリ「熱い月」。この作家もロムロ・ガジェゴス賞を受賞しているが、1993年とずいぶん前になる。これは1983年の作品で、ゴシックロマン風に不死身のファム・ファタールが活躍するなんてすごそう。長く読み継がれているそうなので、それだけおもしろいのだろう。
●この辺は翻訳が出ていてもいいのではないかと思った5冊。
ドイツのペーター・ハントケ「戯曲集」なのだが、「観客罵倒」が引用されていて、これは原文で読んだ。翻訳が出ている筈と思ったが、1977年の白水社「現代世界演劇 17」に入っている。が、ハントケの戯曲集は確かに未訳だ。
フランスのヤン・ポトツキ「サラゴサで発見された原稿」も「サラゴサ手稿」という名前で1980年の国書刊行会「世界幻想文学大系 19」に入っている。だが、これが抄訳で、全文は未刊。原文で2冊組1600ページというのはちょっと現実的ではないが、「サラゴサの写本」という邦題で映画にもなっているし、是非読んでみたい。
イギリスのキャトリン・モラン「女になる方法」はわかりやすく親しみやすいフェミニズムのようで、これは是非読みたい。小説ではなく自伝、その上英語で、イギリスでベストセラーになったようだから、比較的訳される可能性は高いような気がする。期待したい。
スペインのハビエル・マリアス「恋情」。スペインの大物作家で、2001年に翻訳された「白い心臓」を読んだが、正直、あまりおもしろいと思えなかったので、今度こそ、という想いがある。
カナダのローリー・ランセンズ「ザ・ガールズ」。これは双子もの、しかも結合性双生児の話。だから読まないといけないという気がした。「ふたりの結合性双生児が一人称で語る自叙伝」とは、どんな話法なのか想像もつかない。けれどワクワクする。
●あとでまとめてみて、比較的よく知らない国の現代人女性の物語が読みたいらしいということがわかった。以下の6冊が気になった。
ブータン「輪廻の輪」クンザン・チョデン
イラン「灯りは私が消す」ゾヤ・ビールザード
フィンランド「赤い鼻」ミッコ・リンミネン
アルジェリア「ファティマ、辻公園のアルジェリア女たち」レイラ・セバール
南ア共和国「ビューティの贈り物」シンディウェ・マゴナ
ベリーズ「記憶、夢、そして悪夢」ゲイ・ウィレンツ編
●ちょっと気になった2冊
スウェーデンのヨナス・ハッセン・ケミーリ「片目は赤」はスウェーデンの移民問題を扱っているもの。ヨーロッパの各国のサッカー代表チームを見ると、どの国にどんな移民が多いのかなんとなくわかる。フランスのアフリカ系、ドイツのトルコ系、オランダのモロッコ系などは見慣れている。スウェーデン代表は長身の白人のみだったが、これからはモロッコ系も入って来るんだろうなという気がした。
ブラジルのルイス・フェルナンド・ベリッシモ「天使たちのクラブ」はグルメ小説か、サスペンス小説か?ストレートにストーリーがおもしろそうなのだ。2014年はワールドカップイヤーなのだから、少しはブラジルの作品が増えても良い気がする。
ところで、この本はSNSを駆使して選者を見つけたり、ネットに選者探しの進捗状況が残っているくらいなので、出版社のサイトに目次くらいおいてあっても良いと思うのだが、書籍紹介すらないのが不思議だ。
書誌事項:テン・ブックス 2013.12.9 272p 2,100円 ISBN978-4-88696-030-6(eau bleu issue)