 2666ナイト第1回に行ってみた。「2666」のイベントはこれまでも開かれていたが、久野さんが帰国したため、三人で揃って人前に出るのは初めてとのこと。
2666ナイト第1回に行ってみた。「2666」のイベントはこれまでも開かれていたが、久野さんが帰国したため、三人で揃って人前に出るのは初めてとのこと。
「2666」はものすごく量も多いが中身も豊穣。語ることは本当に尽きないと思う。白水社はこの全5回シリーズをまとめて1冊の本として是非出して欲しい。
以下、印象的な部分をメモし、そこから書き起こしたもの。正確性には欠けるが、雰囲気はつかめると思う。小さい会場だから大丈夫だろうと思い後ろの方に座ったせいか、野谷先生の声だけがかなり聞き取りにくく、聞き漏らしが多い。マイクの調整レベルでなんとかなると思うのだが。それだけが残念。
出演:野谷文昭氏、内田兆史氏、久野量一氏
日時:2013年4月26日(金)19:00~
会場:西武池袋本店別館9階池袋コミュニティ・カレッジ28番教室
野谷:おそらくこの本書の読み方は「ニセンキュウヒャクロクジュウロク」。「ニロクロクロク」は通称。
訳の担当は1部、2部、3部が野谷、4部が内田、5部が久野。
内田:2009年に出版するための資料を作るために原書を久野さんと一緒に読んでいた。お互いに「どこまで読んだ?」とメールしあっていたが、久野さんが先に「アルチンボルディ、キタ~!」と言ってきた。訳した部分以外だと、このとき読んだ切りになっているところもある。それで読んでみたら、原書と訳書の差ではなく、再読がこんなに面白いんだと思った。2回読む本だと思った。
久野:『ユリイカ』2008年3月号 新しい世界文学でボラーニョの「ジム」というアメリカ人が主人公の非常に短い短篇を訳したから、このお話をいただいたのだと思う。2009年の夏にボラーニョの原書をもってブエノスアイレスで読んでいた。そのときに作った資料を見返してみたが、あまり感想は変わっていない。最初の読書がまだ終わってないのかなという気がする。全然読み終われない本であると思う。
野谷:頭から読んでいくという読み方以外にも読み方があるのではという説もある。
内田:例えば第4部目線で第1部、第2部を読むという読み方はある。
久野:第5部から第1部、2部を読むと、あれはそうかと思い出すときもあれば思い出さないときもある。読む角度が常に変わっていく。
野谷:舞台が知性や理性のヨーロッパ、アメリカ大陸を経て、混とんとしているメキシコへと物語が進んでいく。みんな自由を奪われるためにサンタテレサに向かう。
内田:アルチンボルディはドイツ人だが、研究者たちは全員ドイツ人以外。スペイン、ポルトガル、イギリス、フランス。外国人としてアルチンボルディの本を読む。
久野:作家に出会って、その作品を好きになって、翻訳たら、その作家に会いに行こうと思う。文学好きなら誰でもやりたくなること。
内田:なんでそんなに会いたがるんだって言われて、「俺たちが会わなきゃ誰が会う」「生きているとわかっているのにどうして会わないでいられようか」みたいなことを言っている場面もある。
久野:ヨーロッパの秩序だった世界で、批評家たち4人が三角関係、四角関係になりながらも研究者としてのライフスタイルを謳歌している。それがアメリカ大陸に入ってくるとカオスの方へ引きずられていく。2部、3部、4部とだんだん壊れていく。最後また5部でヨーロッパの秩序の世界の物語に戻っていく。
内田:第一次大戦に始まって同時多発テロで終わる"暴力の二十世紀"みたいなものが凝縮されている。第1部でエスポノーサが「暴力に暴力を重ねることはなかったんだ」みたいなことを言うが、第4部に至っては暴力の上に暴力を塗り重ねていって、何が元にあったのかが見えない。自分はそうしたいわけではないのに、どんどん飲み込まれていく。第2部のアマルフィターノはチリから亡命してメキシコに行かざるを得ず、第3部のフェイトは本来全然関係ないのにサンタテレサに取材に行く。だんだん自由を奪われていく。第5部も暴力的なシーンは出てくる。
野谷:自分の訳したところでイチオシのところは?第1部の好きな箇所はたくさんあって、アフォリズム的な、メモしたいようなセリフがたくさんある。一つは、リズかアルチンボルディの2冊目の本を読み、たまらず雨の中を飛び出していくところ。すごく高揚感がある。また、夜のブレーメンの夜に発光しているシーンは美しく、訳していて楽しかった。「音楽隊」とは書いてないが明かに「ブレーメンの音楽隊」のイメージ。
この人の作品を翻訳をやっていると、夢を見てしまい、よくうなされた。それは何故か考えたが"文体がポエティック/詩的"だから合理性と違うところを刺激され、その刺激で夢を見るのではないかと思う。
内田;数えてみたら死体は110体(女性のみ)。
久野:ブエノスアイレスで翻訳していた。時差はちょうど12時間。つまり日本時間の朝がこちらの夜。寝ようかなという時間にメールをちらと見ると、出版社から細かい内容のメールが来ていて、どうしてももう一回やろうかなと思ってしまい、本当に寝られなくなる、というようなことが何度もあった。校正用の赤い細いボールペンがなくて困った。出版社にお願いしたら大量に送ってくれた。
内田:「2666」を翻訳してしばらくして、研究計画書を出さなくてはならなくなった。「○○について考察する」て書いたら「絞殺する」と出て、「2666」が自分のパソコンにまで入り込んでいるのだと衝撃でした。
野谷:第2部にアマルフィターノの洗濯物干しにつり下げられた本が出てくる。それはデシャン(Marcel Duchamp's Unhappy readymade, 1919)の模倣。
「助けてくれ」と、いろいろな声かきこえてくるシーンがある。それは砂漠で殺された女性たちの声かなのか、アマルフィターノ自身の声なのかわからない。
第3部はフィクション的な文体でアメリカの小説を意識している。5部構成で、部ごとに五種類書き方を変えている。
インカの彫像のうなものが出てくるが、解答がない。そうやって全部こちらにたまっていく。
内田:便器が欠けている話が出てくる。失うとか欠けているとか、喪失・欠落が繰り返し出てくる。
久野:片足、片目、空白といった言葉がよく出てくる。
内田:第1部にモーリーニが右手を切った画家に会いに精神病院へ行くシーンがある。
久野:5部にも精神病院が出てくる。
内田:2部にもアマルフィターノの奥さんが精神病院に行く。閉じこめられている、というようなイメージの使い方か?ラテンアメリカはヨーロッパの精神病院だみたいなことをボラーニョがどこかで言っていたような気がする。ヨーロッパの狂気がラテンアメリカに閉じこめられているというような意味か。
久野:アルチンボルディは西欧的というよりは東欧的で、東ヨーロッパは西ヨーロッパの辺境の扱いをされている。ラテンアメリカもヨーロッパの辺境の扱い。
野谷:物語の進行の中で、メディアがかわっていく、手紙→電話→Eメール。
久野:以前の物語はどんな話も最終的には歴史というかヒストリーに落ち着いていった。ひとつにはならない話、複数の世界の話になっていくところが前の物語と違う。
野谷:同時多発的で、中心がいくつもある。
内田:第4部の元になっているセルヒオ・ゴンサレス(・ロドリゲス。実名で4部に登場するジャーナリスト。)「砂漠の骨」(Bones in the Desert)というシウダーフアレスの女性殺人事件を扱ったフィクションだが、ジャーナリスティックな作品がある。
この本をボラーニョが読んで、「ラテンアメリカに今なお生きている伝統は二つしかない。それは冒険と黙示録である。」と言った。セルヒオ・ゴンサレスの本は黙示録である。ボラーニョが「2666」でやろうとしたことは、この"黙示録"的な部分をもつ"冒険"ではないかと。
野谷:「野性の探偵たち」は冒険。
内田:「野性の探偵たち」の方がラテンアメリカで売れたのはわかる。
第4部の好きなところ。捜査官フアン・デ・ディオス・マルティネスとその恋人エルビラ・カンポスのマンションから見る風景や二人の関係が美しい。二人の話が出てくるとちょっとホっとした。
久野:第5部で好きなところ。ハンスの少年時代に図鑑を読み上げるところ。言葉がたどたどしくてかわいい。
野谷:ハンスの妹のロッテの存在も良い。家族小説的なところがある。砂漠を抜けて、第5部の森の世界へやってくる。一種のおとぎはなし。ルーマニアのお城が出て来たりして、ゴシック小説的なところもある。
第4部の殺された女性にわかる限りは名前が与えられてる。柴田元幸さんが言うには、アメリカだったら絶対編集者に削られていたと。全てに名前をつけるのは、アイデンティティを与えているということ。
ボラーニョ的と言える、コーモアが見られる。
内田:ユーモアと言えば、メキシコ的な黒い、女性蔑視的なところも見られる。真面目をつきつめて出てくるユーモアがある。
久野:すごい悲壮感の中で書かれていたと思うが、ユーモアはあると思う。
野谷:彼の文体にユーモアはあると思う。セルバンテスやガルシア・マルケスの文体がボラーニョにはある。バルガス=リョサやプイグには(セルバンテスのユーモアは)ない。
内田:ボラーニョのインタビューに「あなたにとって天国ってなんですか?」という質問があり、解答が「ベネチア」というもので、「あなたにとって地獄ってなんですか?」という質問には「シウダーフアレス」と答えてる。シウダーフアレスにラテンアメリカの暗い面が集約されている。その地獄を描き出そうとしていることは間違いない。だから多くの人に名前がついているし、多くの人にそれぞれの物語がある。
野谷:第4部はみんな吐き気がするとか感想を書いているが。
内田:幼い姉妹が殺されるところは(翻訳が)進められないほどの痛みだった。
質問:3人で分担して翻訳してどうやって文体を合わせたのか。
野谷:白水社の編集担当者がよく調整してくれた。
久野:それぞれへの信頼があった。お互いによくわかっていたので、あの人はこう訳すだろうという予測をもって、自分も翻訳していた。
野谷:長いつきあいなので、こう訳すだろうというのはわかっていた。そこは信頼関係があった。
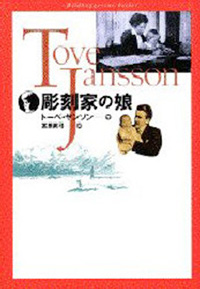 年に1回くらい突然読みたくなるトーベ・ヤンソン。大人向けの小説をいつも読んでいるが、これは自伝的小説で、読者はおそらく中学生以上を想定しているのではないだろうか。ルビをふってある漢字と内容からそう感じた。というのも、ローラ・インガルス・ワイルダーの岩波少年少女文庫に入っている方の小説によく似た雰囲気があるからだ。そして、私はこういうのがとても好きだ。
年に1回くらい突然読みたくなるトーベ・ヤンソン。大人向けの小説をいつも読んでいるが、これは自伝的小説で、読者はおそらく中学生以上を想定しているのではないだろうか。ルビをふってある漢字と内容からそう感じた。というのも、ローラ・インガルス・ワイルダーの岩波少年少女文庫に入っている方の小説によく似た雰囲気があるからだ。そして、私はこういうのがとても好きだ。





