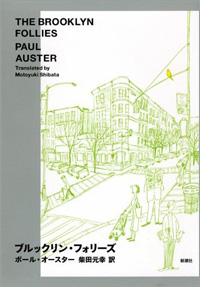君の誕生日は来て、過ぎた/ポール・オースター
 めでたく復刊した『Coyote』No.47に早速、柴田先生訳のポール・オースターが掲載されていた。これは「Winter Journal(冬の日記)」と題したこれまでの人生で出会った女性達を書いた2作目の自伝の中からの一篇だ。
めでたく復刊した『Coyote』No.47に早速、柴田先生訳のポール・オースターが掲載されていた。これは「Winter Journal(冬の日記)」と題したこれまでの人生で出会った女性達を書いた2作目の自伝の中からの一篇だ。
ポール・オースターにとっての大切な女性と言えば、シリ・ハストベットとリディア・デイヴィスとお母さんだろうなと思う。これは、そのお母さんのことを書いた短篇だ。若いうちに結婚した1度目の結婚の子であり、彼女にとっては長子であったオースターはその後の彼女の人生をずっと見つめていくことになる。彼女の人生はいろいろと山あり谷ありで、母親に失望させられることもあったようだ。しかし、小さい頃に深い愛情に包まれ面倒をみてくれたことや、一緒に遊んでくれたことは彼の人生にとって大きいことだったのだろうということが伺える。少し大きくなっての野球チームのつきそいと活躍は印象に残っているという話から、親にとってはしんどさの方が比重の高い「スポーツチームのつきそい」は子供にとっては意外に大事なことなんだなと思い知らされる。
ご祝儀のつもりもあったのだが、短い一篇だけれど、このためだけに『Coyote』を買う価値はあった。「Winter Journal」が翻訳されるのは、順番通りにいくとまだまだ先だが、いつまでもお待ちしています>柴田先生。
Your Birthday has come and gone by Paul Auster. Autumn 2011
「Coyote」No.47 スイッチ・パブリッシング 2012.9.15