ロスト・シティ・レディオ/ダニエル・アラルコン
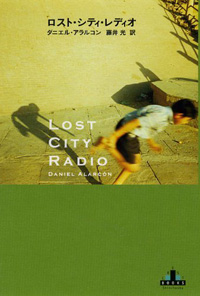 タイトルにある「ロスト・シティ・レディオ」というラジオ番組は日本の戦後にあったという「尋ね人の時間」だ。戦争で行方がわからなくなった、あるいは連絡が取れなくなった人の名前をラジオで読んでもらい、それを聞いた人(本人だったり、周囲の人だったり)がラジオに電話をし、感動の再会を果たすという。
タイトルにある「ロスト・シティ・レディオ」というラジオ番組は日本の戦後にあったという「尋ね人の時間」だ。戦争で行方がわからなくなった、あるいは連絡が取れなくなった人の名前をラジオで読んでもらい、それを聞いた人(本人だったり、周囲の人だったり)がラジオに電話をし、感動の再会を果たすという。
舞台は内戦が終了して10年ほど経った南米の国。その国ではILと呼ばれる反政府組織がジャングルに逃げ込んでいたが、ほとんどが殺されている。内戦は終わってもまだ人々の傷は癒えていない。「ロスト・シティ・レディオ」の女性パーソナリティ・ノーマのところにジャングルからビクトルという少年が訪ねて来る。彼は激烈な戦闘があったという「一七九七村」から村人たちに託されたリストをもって来た。そのリストの中に...。
現在のノーマやビクトルの時間、過去のノーマとレイの時間、過去のレイだけの時間、というように時間が錯綜して物語が進むところ、ストーリーがジャングルと都会を行き来しているところにラテンアメリカ文学らしさを感じて気に入った。直接的には幻想的な部分はないものの、いくつか不思議な雰囲気を感じる場面がある。
戦争の始まった夜の出来事はピリピリとした緊張感あふれているが、一方で暗闇に包まれたバーの中など、ぼんやりと幻視を見ているように読めたりもする。また「タデク」という裁判も奇妙なシステムだ。その国の辺境にあるジャングルの村々では少年に幻覚性の茶が与えられ、酔った少年がそばに寄った人間が罪を背負うべき犯人であるという民間信仰の儀式のようなもの。その儀式に関する論文を危険を冒して発表したレイだったが、その方法である意味復讐を果たすという成り行きが皮肉だ。
ジュノ・ディアス、サルバドール・プラセンシアら南米が出自である北米作家というひとくくりで言うと、ポップで少々アバンギャルドなイメージがあったが、ダニエル・アラルコンはヨーロッパ古典の影響があるのか、多少暗めのクラシカルな雰囲気をもっている。
何故ビクトルがノーマの元へとやってきたのか。教師であるマナウは何故彼を都会に連れて来たのか、ザイールの言う「当然だ」は何故なのか、じわりじわりとそれらの疑問が埋まっていく。その過程が明らかにされる語り口はスリリングだが、冷ややかな感じも受ける。そして途中でもうわかっているレイの消息が明らかになる。
ノーマが最後に気付くのは、自分が長い間懐かしく恋いこがれていたのは夫ではなく、夫とともにいたときの自分だったという言葉。彼女はようやく自分を取り戻すことが出来たのだ。その結果がどうなろうと行動する。私の望んでいた結末ではなかったが、これはこれでいい。おもしろくてガーっと読みそうになるが、スピードを落としてじっくり読んだ方が良いと感じた。
■書誌事項
著者:ダニエル・アラルコン著,藤井光訳
書誌事項:新潮社 2012.1.30 347p ISBN978-4-10-590093-9(クレスト・ブック)
原題:Lost City Radio : Daniel Alarcón, 2007



