オスカー・ワオの短く凄まじい人生/ジュノ・ディアス
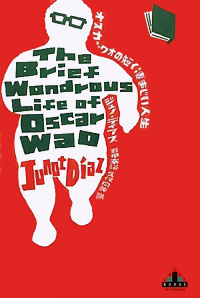 読み終わったとき、「オスカー!」と叫びたい気持ちでいっぱいになった。なんだ、このカタルシスは。予想外に青春バンザイだ。ちょっと泣きそうになった。
読み終わったとき、「オスカー!」と叫びたい気持ちでいっぱいになった。なんだ、このカタルシスは。予想外に青春バンザイだ。ちょっと泣きそうになった。
オスカーの話、姉ロラの話、母ベリの話、祖父アベラールの話。この四つのうち、主人公のオスカーの話が第5章を読み終わるまでの間は一番興味がもてなかった。SFの話がたくさん出てくるせいではない。それは楽しい。自分がアメコミやSFの用語を言葉としては思いのほか知っていることに驚いた。
オスカーのイメージとして浮かんできたのは、以前話題になったスターウォーズ・キッドにメガネをかけた姿だった。遠からずだと思う。少年時代の非モテ話は笑えるが、彼がめげずにチャレンジを続ける姿にはあまり感じるものはなかった。
それよりはロラやベリの話の方が自分には興味がもてる。ロラは母親に認めてもらいたくて仕方がないのに、決して認められない娘だ。母親の呪縛から逃れようと必死なのに逃れられない。弟は溺愛されているのに嫉妬するどころか、自分もともに弟を溺愛している。この物語は古典的な母子の問題で、たいがい母親が強すぎることから発生する事態だ。さらに、ベリの話でトルヒーヨ時代に飛ぶと別のおもしろさが味わえる。辛酸をなめたベリの話を読むと、ロラの章のときのターミネーターっぷりが理解できるようになる。これだけの目に遭えば、強い母親が出来るわけだ。この辺はほとんどの読者の方と異なり、私にはかなり面白いと思えた。
オスカーに話が戻る。成長しても相変わらずモテない。そのくせ努力して自分を変えようとはしないので、イライラさせられる。ユニオールという、ロラへの下心があるとは言え、オタクではない友達がせっかくできたのに、助けてやろうとする彼の努力を無にする。オスカーはどうしようもない頑固さにとらわれている。自分の目的を達成するには自分を変えなくてはならない。でも変えられない。どうにかしたいけれど「僕はこんなふうでしかないんだ!」と主張するも、むなしい。風俗や二次元に逃げないのは、彼が欲しいのは「愛」だからだ。さえないオスカーの話は一度どん底まで行って少しずつ上昇する。このあたりからオスカーに変化が見られ、読む側も少しずつ意識が変わり、ラストまで一気に加速する。
オスカーは本質的には変わらない。しかし、それでも少しずつ変わっていき、ラスト近く決定的に変化する。その成長の物語がこの小説の最大のみどころなのではないかと思う。理想家と言えば理想家の彼が、どういう形で自分の夢を実現するのか。なるほど、あのイライラはすべてこのエンディングのためだったのかと納得する。
解説を読む。この小説はバルガス=リョサの「チボの狂宴」への対抗意識から書かれたそうだが、どんな対抗意識かと思ったら、ドミニカの話なのにペルーの白人が自分のもののように書くのはおかしいだとか、スペイン語圏を去った英語圏の作家だから自分に書く権利はないのかとかだ。誰もそんなこと言ってないし、先に書けばよかったじゃんと思う。作家としてのコンプレックスをバネにして良い作品を仕上げたことは素晴らしいとは思うが。
それからリョサは別にバゲラールのことも「思いやりのある人物」に書いているわけではない。内戦に向かわぬよう政権のバランスをよくとったのは事実だし、リョサたしかにバゲラールを否定的に書いてはいないが、わざわざ物語と直接関係のないトルヒーヨ後の人物の話まで註で書いているところは少々疑問。バゲラールは確かにディアスの言うように実際はひどい奴なんだろうけれど、この小説では関係がない。先達に対しての意識が強すぎて、余計なことをしているなと思う。
ただ「新しい言葉、新しい書き方でないと、トルヒーヨの伝説化に手を貸すことになる」というディアスの切迫感は理解できる。そしてこの小説は新しく興味深い手法を使い、しかしとてもクラシカルな青春小説となった。どちらが面白いかと聞かれると困るが、この小説を読んでから「チボ」を読んだとしたら、かつて斬新だったリョサの手法も慣れてしまって、「歴史小説」のような古めかしさを感じてしまう可能性はあるだろう。
「ナード」と「オタク」の違いは解説のおかげでよくわかった。オスカーはナードにオタクカルチャーを足してできあった人物で、おそらくアメリカには日本のような二次元しか見えないといったオタクはいないのだろう。ナードに対する言葉として「ジョック」に触れられていたが、これこそ私が昔からおそろしくて仕方がなかったアメリカのハイスクールのヒエラルキーだ。男性の場合、このヒエラルキーの頂点はスポーツマッチョ。女性の場合はチア・リーダーだ。きれいで自信たっぷりで、常に自分の身を磨いている女の子たち。「プロム」なんか日本にやってきた日には、自分は「キャリー」になるに違いないと思っていたくらいだ。日本人でよかった。日本にはチアリーダーはそんなにいないし、アメフトもない。もちろんヒエラルキーはあるが、アメリカほど明確ではなく曖昧だ。自分も充分にナードでオタクだが、できれば自分は「ギーク」でありたいと少し思う。
私はどれだけこの翻訳書が出るのを待っていただろう。最初に知ったのが2009年1月の杉山晃先生のブログ。このときは翻訳が出るといいな、くらいの感じだった。2010年3月白水社での都甲幸治氏と藤井光氏の対談が掲載され、そこで翻訳が進められていることを知り、新潮クレストブックのラインナップとしてサイト上に載ったのがミランダ・ジュライの「ここではないどこか」が発売された8月頃だった。当初は初秋にはと聞いていたのがずるずると後れ、年明けになり、ついに2月25日と出たときには「いよいよ」と思ったものだ。
入手したがすぐにはとりかかれず、さて、と1~2ページとりかかったところで、3月11日がやってきた。すると、本というか、一切の物語を受け付けられなくなってしまった。あれだけ楽しみにしていたのに。確かに雑事に追われゆっくり本を読む時間はなかなかとれないが、それ以前の問題で気持ちが向こうとしない。
思うに、人は世界中の不幸や悲惨がすべて自分の身に起こりうると想像してしまったら、正気ではいられないのではないだろうか。悲惨や不幸を自分とは違う場所で起こることと想定する、それは正気を保つための防波堤のようだ。まず大前提としてこの防波堤がしっかりとできてないと、物語を読むことは無理なのかもしれない。7年ほど前、あることがきっかけで、この防波堤の一部が崩れてしまった。以来、特定の物語を一切受け付けなくなった。というよりは、読むとどういう心理状態になるかが想像できるために避けるようになったというべきか。今回の地震の後、防波堤がすべて決壊してしまったようだった。津波が来て水の中をもんどりうって流される、クルマの中に閉じこめられたまま流される、何かにつかまってなんとか津波をやり過ごしたものの、波が引かなくて動きがとれず、衣服をすべてはぎ取られた状態で一晩中東北の雪に耐える、そういった被災者の体験が己の身に起こってもまったくおかしくはなかったと感じるようになってしまった。テレビや動画はできるだけ見ないようにしていたにもかかわらずだ。すると、どういうわけか、物語がすべて怖く感じられるようになる。その中にどんな悲惨や不幸が入っているかわからないからだ。
仕方なく、防波堤が立ち直るまでのつなぎと思い、Togetter(これは刊行直後に作成し始めたもの)やNAVERまとめをまとめながらぼんやりと過ごしていた。4月に入り、少しずつ気持ちが落ち着いて、ようやく読み始めることができた。始めたら、時間がないなりにも、自分にしては一気に読めた。面白かった。これはきっといろいろな意味で一生忘れられない本になるだろうと思う。
【お知らせ】エンドレスになってしまうので、自分の読了と同時にTogetterをまとめるのを止めます。翻訳者の先生や註を書かれた評論家の先生にまで取り上げていただき、若干おもはゆいTogetterデビューでした。
■書誌事項
著者:ジュノ・ディアス著,都甲幸治,久保尚美訳
書誌事項:新潮社 2011.2.25 414p ISBN978-4-10-590089-2(新潮クレストブック)
原題:The Brief Wondrous Life of Oscar Wao : Junot Diaz ,2007
■目次
第一部
第1章:世界の終わりとゲットーのオタク(1974―1987)...オスカー
第2章:原始林(1982―1985)...ロラ
第3章:ベリシア・カブラスの三つの悲嘆(1955―1962)...ベリ
第4章:感情教育(1988―1992)...オスカーとユニオール
第二部
第5章:かわいそうなアベラード(1944―1946)...アベラード
第6章:取り乱した者たちの国(1992―1995)
第三部
第7章:最後の旅
第8章:物語の終わり



