フェアプレイ/トーベ・ヤンソン
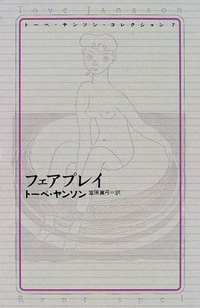 私はガッチリとムーミン世代なのだが、児童文学にあまり興味なく、フリークがいることは知っていたが特にトーベ・ヤンソンに興味はなかった。きっかけになったのは2001年に放映された「北欧トレッキング紀行森と湖の国 ムーミン谷への旅~フィンランド~」というNHKのドキュメンタリー番組だ(2010年1月に再放送あり)。故・岸田今日子のナレーションで、後に「かもめ食堂」に主演する小林聡美(ムーミン世代)が案内役だった。この番組でクルーブ・ハル島が紹介され、見ると島も小屋もあまりに小さい。30年間もここで夏を過ごしたのかと驚いた。水道も電気ももちろんない。自然と向き合うしかないのだ。
私はガッチリとムーミン世代なのだが、児童文学にあまり興味なく、フリークがいることは知っていたが特にトーベ・ヤンソンに興味はなかった。きっかけになったのは2001年に放映された「北欧トレッキング紀行森と湖の国 ムーミン谷への旅~フィンランド~」というNHKのドキュメンタリー番組だ(2010年1月に再放送あり)。故・岸田今日子のナレーションで、後に「かもめ食堂」に主演する小林聡美(ムーミン世代)が案内役だった。この番組でクルーブ・ハル島が紹介され、見ると島も小屋もあまりに小さい。30年間もここで夏を過ごしたのかと驚いた。水道も電気ももちろんない。自然と向き合うしかないのだ。
この番組ではさらりとしかふれていなかったが、トゥーリッキ・ピエティラという女性の存在をここで知った。調べてみると、トーベ・ヤンソンの生涯のパートナーだったようだ。私はこの手の話が大好きで飛びついた。トーベ・ヤンソンがレズビアンだったかどうかは、この際私にとってはどうでも良いことで、女性どうしが長年連れ添って生きたというのがついいいなと思ってしまうのだ。例えばガードルード・スタインとアリス・B・トクラスとか。それは仲の良い老夫婦を見るのに一見似ているが、真逆でもあったりする憧れだと思う。
この作品はヤンソンのエッセイ「島暮らしの記録」を小説にしたようなものだとこちらで教わって、「フェアプレイ」から読むことにした。短いエピソードを積み重ねた物語だが、舞台はフィンランドの小さな島だけではない。ヘルシンキの街中だったり、旅行したメキシコの遊園地、アリゾナ州のフェニックスなど様々だ。ここまで来るのに様々に攻撃されたことだろうと思う。長年苦労して来て、自分一人の足で立っている人たちだからこそ、こうなるのかもしれない。強い独立心と心地よい依存。
微妙にかみ合ってない二人の会話がおもしろい。これは行き違いなどではない。言いたいように言っているからそうなるのだ。省略されている部分が実はすごく多くて、言ってない言葉がたくさんあるから、かみ合ってないように見えたりするのだ。
二人とも芸術家だから年をとっても野心がある。小説で苦しんでいるマリにヨンナがアドバイスもするし、パリに留学しようという話で悩んだり、様々に葛藤がある。二人の間も仲良しこよしではまるでなく、ケンカばかりだ。信頼できる相手だからこそ、出来るケンカなんだなと思う。フェアプレイ。対等の関係って、こういうことなのか。
さらに、二人の話は二人だけのものではない。共通の友人もいるし、マリの弟もいる。70歳近いのに92歳の老人に小娘扱いされてがっくりしたり、50歳程度の女性を弟子にとり、ご執心のヨンナにマリがひどく腹を立てたりする。
70歳近い老女が二人でボートをこいだり、鴉を撃ったり、魚のかかった網を引き上げたり、ボートが霧で動けなくなったり、自然とごく普通につきあっている。孤島で夏を過ごすことは子供の頃から毎年やっていたヤンソンにとっては当たり前のことだったのだろうけれど、それはとてもまね出来ないなと思う。
小説家・挿絵画家のマリがヤンソンで彫刻家で元教師のヨンナがトゥーリッキのようだが、両方にトーベ・ヤンソン自身が反映されているのかもしれない。マリの母親がよく出てくるが、長い間3人で暮らしたそうだから、それも加味されているのかもしれないと思った。
いろいろなことがあって、年老いて、最後に信頼出来る友人と一緒にいられたらいいなと思うのは普通じゃないかなと思うのだけど...順番からすると女性の方が長生きなんだし。同性だと言わなくてもわかり合える部分が多いが、その分感情がぶつかりやすい。異性だと、わからないからこそ一からきちんと話さなければならないという気構えがあり、それがいい意味での距離感をもてれば、一緒に暮らすには男女の方が良いのかもしれない。でも、それも年をとると面倒くさいと思う部分が大きいのかもと思ったりもする。この辺は男性同士にはない感覚だろうな。
それにしても、ファスビンダーを一緒に夜中に見てくれる友人がいたら、いいなぁ。
■著者:トーベ・ヤンソン著,冨原眞弓訳
■書誌事項:筑摩書房 1997.12.20 (トーベ・ヤンソン・コレクション) ISBN4-480-77017-8




