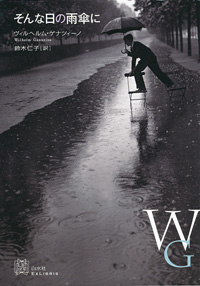愛と狂気と死の物語―ラテンアメリカのジャングルから
 ウルグアイ出身のアルゼンチン作家オラシオ・キローガ(1878~1934)(1878~1934)の短編集。「オラシオ・キローガ」と音引きを入れた方が過去の作品を検索できるだろう。「オラシオ・キロガ」というのは日本では童話作家だ(同一人物だが)。「ラテンアメリカ短編集」などで読んだことがあるが、一冊まるごとは初めてだ。というのも、一冊まとめて邦訳されたのが初めてだから、当然だろう。
ウルグアイ出身のアルゼンチン作家オラシオ・キローガ(1878~1934)(1878~1934)の短編集。「オラシオ・キローガ」と音引きを入れた方が過去の作品を検索できるだろう。「オラシオ・キロガ」というのは日本では童話作家だ(同一人物だが)。「ラテンアメリカ短編集」などで読んだことがあるが、一冊まるごとは初めてだ。というのも、一冊まとめて邦訳されたのが初めてだから、当然だろう。
ボルヘス、ガルシア=マルケスら以前の作家で、ジャングルの不思議の話は好きだ。特に最後の「アナコンダ」は蛇の特性がそれぞれ生かされた物語でおもしろい。登場する人間たちは比較的簡単なミスで死んでしまう。厳しい自然の中を生き抜いてきたわりにはあっさりと死ぬ。それがジャングルというものだという主張が見える。
本書がもちろん刊行されたことに、もちろん意義はあると思うのだが、どうしても「なぜ今」感が抜けない。ラテン・アメリカのブーム以後の作家がようやく邦訳されている昨今、なぜ今それ以前の作家のものを出すのだろう...?という気がしてならない。カルチャーセンターでのスペイン語講座のまとめ、という本書の由来も若干「残念」という感じがする。二束三文の翻訳料か、奨学金でもない限りラテンアメリカの翻訳書なんて出にくいのは理解できるが、現代企画室にも彩流社にも明らかに新しい読者を開拓しようと意欲が見えないのは残念だ。この厳しいジャンルで「売れること」「新規読者を開拓すること」を目指して本を企画・刊行しているのは白水社くらいなものだ。ラテンアメリカ文学の翻訳を読む連中なんて、どうせ小さな小さな村だから、どうでもいいと軽んじられている気が少ししてしまう。
そうは言っても買いますが、義務感からとしかいいようがないな、特に彩流社の場合。
■著者:オラシオ・キローガ著,野々山真輝帆編
■書誌事項:彩流社 2010.7.1 ISBN978-4-7791-1540-0
■内容:
一粒のダイヤ
漂流船の怪
メンスーのこと
丸太釣り師
野生の蜂蜜
平手打ち
不毛の地
白い昏睡
人間になったトラ─フアン・ダリエン
死にゆく男
急行列車の運転手
羽を抜かれたオウム
故郷を追われて
アナコンダ