知恵の木 ピオ・バローハ
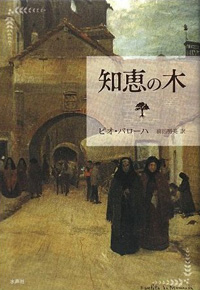 100年以上前のマドリーの様子を知ることに何の意味があるのかというと、やはりあの不思議なスペイン人気質というものをなんとなく実感のあるものにするために…とでも言うべきか。本当は今現在のこういう下町の姿とか、知ることが出来たら良いのになぁと思うのだが。それにしてもスペイン文学とはちょっと思えない、日本やドイツの近代文学くささというか教養文学くささを感じる。知識階級の青年はどうあるべきか、社会に対してどのような態度をとるべきか、というような内省的な内容。社会の不正に対して憤るが、生活もせねばならない。真っ向から悲惨な貧困を目の当たりにしてやられてしまったり、田舎の人々の旧く頑なな精神に触れ、誤解を受けたり、とよくある話だが、まるで明治の文豪の書いたもののようだ。時代としては同じものなので、当然と言えば当然か。
100年以上前のマドリーの様子を知ることに何の意味があるのかというと、やはりあの不思議なスペイン人気質というものをなんとなく実感のあるものにするために…とでも言うべきか。本当は今現在のこういう下町の姿とか、知ることが出来たら良いのになぁと思うのだが。それにしてもスペイン文学とはちょっと思えない、日本やドイツの近代文学くささというか教養文学くささを感じる。知識階級の青年はどうあるべきか、社会に対してどのような態度をとるべきか、というような内省的な内容。社会の不正に対して憤るが、生活もせねばならない。真っ向から悲惨な貧困を目の当たりにしてやられてしまったり、田舎の人々の旧く頑なな精神に触れ、誤解を受けたり、とよくある話だが、まるで明治の文豪の書いたもののようだ。時代としては同じものなので、当然と言えば当然か。
医学生~医者になって直後くらいの時期の若い青年の物語。途中叔父とのだらだらとした会話を挟んで、学生時代と医者になってからの苦労話が語られる。途中、幼い弟に心を砕くところは泣けるが、それ以外はどうにも理屈専攻でちょっと面倒くさい青年だ。最後の方にようやく落ち着いたかと思うと、いきなり急転直下で気の毒。
スペインの田舎から都会に出てきたちょっと知識階級の若い連中はみんなドン・ファンにあこがれ、恋と決闘に明け暮れることを夢見ていたなんて、笑える。そうか。だからみんなあんな感じなんだ、と少々合点がいく。サッカーとか、フランコとか、バスクだカタルーニャだ、その辺が盛り上がる前の段階での旧いスペインのお話だが、彼らの根っこが少しわかったような気がした。
家庭環境や医者として田舎に赴任したところまではピオ・バローハの自伝的要素多数とのこと。が、それ以後はまるで違う、多作なスペイン作家。戦前が中心だけれど、1956年没。
■著者:ピオ・バローハ著, 前田明美訳
■書誌事項:水声社 2009.5.30 331p ISBN4-89176-725-1/ISBN978-4-89176-725-9
■原題:El árbol de la ciencia, Pío Baroja ,1911



