まぼろしの王都
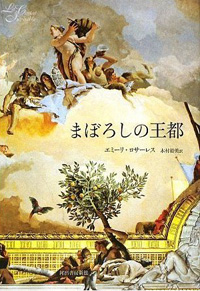 売れたし評価も高いというカタルーニャ文学が翻訳されたら、とりあえず読まなくては。「まぼろしの王都」は18世紀の建築家・アンドレア・ロセッリの「見えないまちの回想記」とそれを翻訳しているバルセロナの画商エミーリ・ロセルの物語がそれぞれ一人称で語られ、交互に出てくる。エブロ河のデルタ地帯にあるサンカルラス・デ・ラ・ラピタという街に過去に建設されたと伝えられる「見えないまち」があるという。エミーリは突然送られてきた回想録を翻訳しながら、幼い頃の記憶をよみがえらせる。スペインのデルタ地方の政治状況、絵のありかを探る話、3人の女性との絡みなど、むしろ現代の方が興味深く、やはり回想録は添え物なように思える。バランスとしては悪くはないが、歴史物が好きな人には若干物足りないかもしれない。
売れたし評価も高いというカタルーニャ文学が翻訳されたら、とりあえず読まなくては。「まぼろしの王都」は18世紀の建築家・アンドレア・ロセッリの「見えないまちの回想記」とそれを翻訳しているバルセロナの画商エミーリ・ロセルの物語がそれぞれ一人称で語られ、交互に出てくる。エブロ河のデルタ地帯にあるサンカルラス・デ・ラ・ラピタという街に過去に建設されたと伝えられる「見えないまち」があるという。エミーリは突然送られてきた回想録を翻訳しながら、幼い頃の記憶をよみがえらせる。スペインのデルタ地方の政治状況、絵のありかを探る話、3人の女性との絡みなど、むしろ現代の方が興味深く、やはり回想録は添え物なように思える。バランスとしては悪くはないが、歴史物が好きな人には若干物足りないかもしれない。
まぁ、要するにカルロス3世がデルタ地帯に作ろうとした都がまぼろしの都になってしまった理由は一人の鈍感な男のせいだという話。チェチーリアがペテルスブルクへ行った後から何故宮廷やサロンを飛び回るようになったのか、このロセッリという鈍い男はよくわかってない。だから現地妻なんか作って、しかもそれをわざわざ知らせている。二人の間が友情だけになったなんて大間抜けにも信じているなんて、本当に馬鹿。夫にもバレたし、もう続けていられないけれど、あなたの夢に力を添えるため、ロビー活動を続けてきたのに、なんてこと、あの絵の意味がわからなかったの?とばかりにチチェーリアは最後に爆発する。そのせいで街の建設は頓挫する。
けれど、一方現代の世界では、回想録をアリアドナの真意を理解し、若い頃の傷を克服して、新しい人生を得ることが出来る。ロセッリの方も夢は破れたが新しい人生を得ることが出来たのも確かだが、エミーリの方が大人だなと思う。ソフィアの策略に乗らなかったりするし。
ともあれ、最後の父親の件は余計な気がする。その後、絵はどうなったのか、アリアドナとの関係は?などの方が知りたかった。
■著者:エミーリ・ロサーレス著,木村裕美訳
■書誌事項:河出書房新社 2009.8.30 338p ISBN4-309-20524-0/ISBN978-4-309-20524-3
■原題:La Ciutat Invisible, Emili Rosales, 2005





