皇帝ペンギン
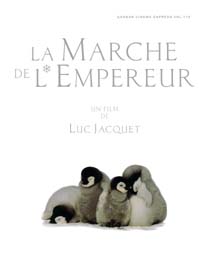 原題:La Marche de L'EMPEREUR
原題:La Marche de L'EMPEREUR
2005年 フランス 86分
監督:リュック・ジャケ
声:ロマーヌ・ボーランジェ、シャルル・ベルリング、ジュール・シトリュク
数年前、NHKのドキュメンタリーで初めてエンペラー・ペンギンの生態を見たとき、何という非合理的というか合理的というか、その不思議な生き方にびっくりして、誰彼かまわず周囲に説明してまわったことがある。それを覚えていてくれた人が今回この映画に誘ってくれた。
南極大陸の海で狩りをしながら生息しているエンペラー・ペンギンだが、南極大陸にはアデリー・ペンギンとエンペラー・ペンギンしかいない。他の南半球のペンギンはみなアフリカ大陸やアルゼンチン、マルビナス諸島などに生息している。その中でもエンペラー・ペンギンは特におかしな生態だ。
冬が来る前に彼らは沿岸から内陸部へ一斉に旅を始める。これが示し合わせたかのような動きで見事なペンギンの行列となる。コロニー(営巣地)は40ヶ所くらいしかないが、旅には1ヶ月かかったりするのだ。ブリザードが比較的よけられる、岩陰などが多いようだ。そのコロニーでオスとメスが出逢い、交尾し、卵が産まれるのを待つ。この間3週間ほど、夫婦は一緒にいる。そして、卵を産み落として栄養状態の悪いメスは卵をオスに預け、海へ向かう。自分と雛のため、栄養補給に行くのだ。卵は足の上においてあたためている。外気に触れる時間がほんの少し長くなっても、卵は死んでしまう。この卵の預ける行動がダンスのようだと映画では言う。
メスが出掛けた後、オスは更に2ヶ月、絶食したまま卵を暖め続ける。男だけになったコロニーではオスたちががっちり固まって、押し合いへし合いして動いている。これはハドリングといって、熱を産み出し、場所を変えることによって、熱を無駄にしないための集団行動だ。ブリザードの中、ハドリングに励むオスの背中には明らかに「男は辛いぜ」と書いてある。
そのうち卵が替えって雛が生まれるが、まだメスは戻らない。オスが胃壁を崩してやっとのことで雛を食べさせている。メスはコロニーに戻ったとき、大勢のペンギンの中から自分のパートナーと自分の子供をちゃんと見つける。そのときのメスは明らかに「あんた、今帰ったわよー」と翼をバタバタさせている。
そして交代にオスは雛をメスに預け、自分はえさをとりに海に行く。この雛を預けるときに失敗すると、死んでしまうこともある。オスの方も栄養状態最悪で海に向かうので途中で死んでしまうこともある。そのため、メスの数より圧倒的にオスの数の方が少ない。
メスは一生懸命雛を育てる。が、ある程度の大きさになったところで、寒さもゆるみ、メスの足の中から出られるようになると、もうえさがなくなったメスは雛をほうって再び海に向かう。すると雛は雛でかたまってクレイシ(保育所)を作る。オスが戻って来て父親と会ったり、戻るオスと海に向かうメスが出会ったりもするが、どうやら基本的にもう雛の面倒は見ないようだ。そしてある日雛たちも海に向かう。エンペラーペンギンはどうやら独り立ちに際してエサの取り方を教えたりはしないようだ。
ほとんど外敵のいない場所をわざわざ選んでの繁殖行動なのだが、少し海鳥がいたりして、時折雛が食べられてしまったりする。だが、クレイシは雛の個数が多く、数の力で固まっているとなかなか海鳥も近づけない。さらに、クレイシの近くには必ず数羽の大人がいて、雛を守っていたりする。しかし、オスもメスも出掛けてしまっているから、クレイシを作っているのに、いったいこの大人ペンギンはなんだろう?
この映画のパンフレットで疑問は解決したが、やはり途中で雛をなくしたり、卵をなくしたりして、えさをやる必要がなく、栄養状態の良い成長個体だったり、逆にまだ繁殖できない3年未満のペンギンだったりするらしい。まさに保育士のようだ。
そもそも、ペンギンは陸上でのよちよちぶりと水中での素早い動きとのギャップが面白いので好きだった。種類の数が限定されているので覚えやすく、生息地も限られているので把握しやすいのも好きな理由だ。
だが、エンペラーペンギンはどうにもこうにも変だ。何が変って、極寒の南極大陸の、しかもエサのない場所へわざわざ大移動しての繁殖。しかも何往復もする。沿岸部では海獣がいて雛が食べられてしまうためだそうだが、合理的なんだか、非合理的なんだか、よくわからなくなってしまう。
フランス語でペンギンが話しているのも、やっぱりヘンな感じだ。






