ベリッシマ
 ■原題:Bellissima
■原題:Bellissima
■制作年・国:1951年 イタリア
■監督:ルキノ・ヴィスコンティ
■製作:サルヴォ・ダンジェロ
■脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/フランチェスコ・ロージ/ルキノ・ヴィスコンティ
■撮影:ピエロ・ポルタルーピ/ポール・ロナルド
■助監督:フランチェスコ・ロージ/フランコ・ゼフィレッリ
■出演:アンナ・マニャーニ/ヴァルテル・キアーリ/ティーナ・アピチェッラ
ヴィスコンティ、唯一の喜劇映画(オムニバス「われら女性」を除く)であり、2時間以下の作品。ネオレアリスモ映画であることは確かだが、それはともかく、イタリア映画が得意とする下町人情ものだ。それはそれで好きだが、ヴィスコンティらしくないので、あまり期待はしていなかった。しかし、意外と良い映画だった。
アンナ・マニャーニは「郵便配達は二度ベルを鳴らす」で起用しようとしたが、撮影開始直前に妊娠が発覚したため降りてもらったという経緯があり、この作品を制作のサルヴォ・ダンジェロから持ち込まれたとき、マニャーニなら撮るといったくらいだから、よほど気に入っているのだろう。ロベルト・ロッセリーニ監督の「無防備都市」の主役でネオ・リアリスモの代表的な女優と言われ、「バラの刺青」でアカデミー主演女優賞も受賞している国際的にも有名な女優である。このとき40過ぎくらいの年齢だったが、このウエストを維持しているのはすごい。もちろん巨乳だってしっかりと形が保たれている。女優魂だなぁ。
マニャーニが扮するのは5歳の娘と夫の3人でアパートに住んでいるマッダレーナ。医薬分業のイタリアでは注射の資格をもった看護婦に注射してもらわなくてはならない。彼女は腕の良い看護婦で、患者の家まで出張し治療をして稼いでいる。彼女はたくましく、よく喋り、生活力があって家族思い。中年になっても色っぽいが意外と貞節でまじめ。感情の起伏が激しく、怒るし泣く。でも、プライドはとても高く、押しが強い。イタリアのおかみさんと言えば、彼女が元祖だ。イタリア下町人情ものはやっぱりいいなと思う。とにかく、見ていて元気が出る。ヴィスコンティを見終わったら何かまた見よう。
この映画、要はマニャーニの演じる母親が娘を映画のベリッシマ(美少女)コンテストに合格させようと奮闘するステージママぶりが描かれている。詩の朗読をさせたり、バレエを習わせたり、写真を撮ったり、衣装を作ったり、ローマ中を駆けめぐる。娘のアンナはとてもかわいいが、母親の言われたままにけなげに頑張っているだけで、やりたくてやっているわけではない。母親の方は娘の幸せのためと固く信じ、貧しく無教養であるがゆえの自分と同じ苦労はさせたくないとばかりに、猪突猛進する。
マッダレーナは撮影所に出入りする青年アノヴァッツィと知り合い、コネとして使おうとするが、彼からコネをつかむためには必要だと大金を要求される。家を買うという夢があって貯金したお金だが、娘のためならと即座に支払う。だがアノヴァッツィはそれで自分のバイクを買ってしまう。マッダレーナはアノヴァッツィにだまされたことはすぐにわかるが、決して恨みつらみを言うわけではなく、娘が合格するという結果が出ればそれでいいと言い放つ。「昔から人が良く騙されやすいと言われる」と、あっけらかんと笑ってみせる。娘が必ず受かると信じているからだ。豪快だなぁ。でも、しっかり試写に潜り込めるように手配もさせた。
アノヴァッツィの母親も彼に自分の果たせなかった夢を託し、期待を寄せてあれこれと指図するという。彼が紹介した撮影所の編集係の女性もかつてはちょっとした女優だったが、ちやほやされていい気になって、突然ほされてしまったという話をする。そういった話を聞きながら、少しずつマッダレーナの中に疑問が生まれる。
マッダレーナは無理に頼んで監督やスタッフたちがコンテストで撮影したフィルムを見ている姿を映写室から覗く。スクリーンに映った娘は何度吹いてもろうそくの火を消せないし、詩の暗唱もできず、そして泣き出してしまう。それを笑うスタッフたち。アノヴァッツィも金をもらっているくせに「フィルムの無駄」と言い放つ。監督だけは笑っていない。マッダレーナは嘲笑に耐えられず、スタッフらに対して娘が笑い者にされたことに怒りをぶつける。そしてよろよろと撮影所を出て行く。娘は疲れて眠ってしまい、マッダレーナは泣きながら娘を抱きしめる。
このシーンなのだが、確かにひどいのだ。誰も泣いている彼女をなだめようとすらせず、ひたすらフィルムを回し続けるのが特にひどい。結局マッダレーナの娘が採用されることになり、支払ったのよりも遙かに大金が入ることになるのだが、即座に断る。「今度はどうやって娘を笑いものにするつもり?」と。
マッダレーナは最後になってようやく気づく。娘のためにと思ってやってきたことが、娘のためにはならないということが。映画界にいるひどい連中をみて、こんなところに入れることは出来ないと思ったのだろう。自尊心を傷つけられることが何よりつらい。そして、何が本当に娘のためか、やっぱりわかることができるのだ。
夫も彼女がアパート購入資金を使ってしまったことを責めず、なぐさめる。彼女はこれから死にものぐるいで稼いで家を買うと言い切る。やっぱり生活力もある女性はカッコいい!「昨日、今日、明日」のソフィア・ローレンも自分で稼いで、マストロヤンニを食べさせていたっけ。
この映画の中でアパートの広い中庭で映画上映が行われている。ローマっ子は映画が好きなのは知っているが、これはすごい。壁をスクリーン代わりにして、映写機で写しているのだと思うが、誰か映画の好きな人が主催しているのだろう。家庭にテレビがある時代ではないので、これが大事な娯楽なのだろう。マッダレーナも映画が大好きだ。だから映画に出られるということは、本当にすてきなことだと思いこんでいるのがよくわかる。無知だが素朴で愛情たっぷりのイタリア女性を満喫した。衰退の美学を見ようと思っていたヴィスコンティ全集だが、まるで違う方向で楽しんだ一本だった。しかし人間の尊厳は下町の無学な女性でも、貴族でも同じだから、プライドの高い人間を描くところは、やっぱりヴィスコンティらしいとも言えるだろう。
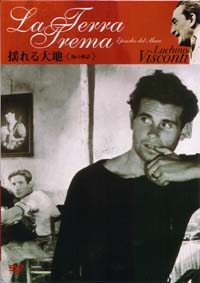


 NHK 2005.1.15
NHK 2005.1.15 NHK 2004.12.25(2005.1.14再放送)
NHK 2004.12.25(2005.1.14再放送)






