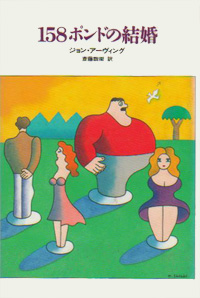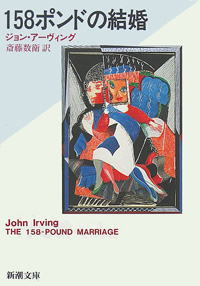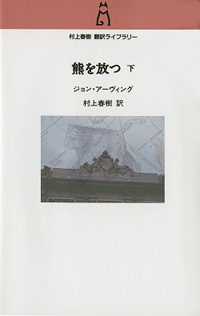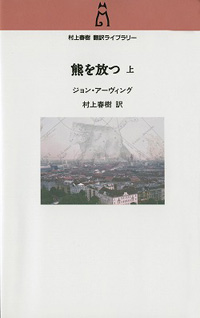The 158‐Pound Marriage, 1973-74
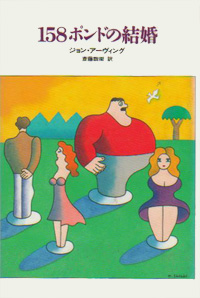 斎藤数衛訳 サンリオ 1987.1.15 1,500円 ISBN4-387-86152-5
斎藤数衛訳 サンリオ 1987.1.15 1,500円 ISBN4-387-86152-5
歴史小説家である「僕」には、ウィーンで数奇な育ちをしたウチという妻がいる。一方、「僕」の友人で大学でレスリングのコーチをしているセイヴァリンは、ウィーンで知り合ったヤンキー娘のイーディスと結婚した。これら2組のカップルのユーモラスで鮮烈な夫婦交換の物語を通して浮かびあるがる現代人の内面風景とは?『熊を放つ』と『ガープの世界』をつなぐJ・アーヴィング会心の力編。
ウィーン、りんご園、新聞記者を逃したタクシー運転手、熊などに続き、戦時中に動物園に入って檻から逃がそうとして(あるいは食糧難だったために食べようとして?)食べられてしまった男の話など「熊を放つ」から引き続き使われるモチーフが出てくる。今回初めて出てきたのは「レスリング」という要素で、前回の「バイク」に代わるものだ。
物語はアメリカの大学での話だが、登場人物のうち二人は戦前のオーストリア出身だ。セイヴァリンとイーディス、ウチと僕の2組の夫婦はそれぞれ見た目にも不釣り合いなカップル。前者は体格の良い背の低いレスラーと上品な教養ある作家、ドイツの子牛のような妻と年齢より老けて見える細身のインテリ歴史作家。レスリングコーチと歴史作家が同じ大学の教員というあたりがそもそも変てこりんな話だ。
このウチという女性は学生の頃のドイツ語会話の先生の奥さんを彷彿とさせる。本当に人間か?と思えるほどお尻がでかい。単なる日本によくいるデブとは違って、はじけそうなくらいパンパンに張ったお尻なのだ。
この物語はゲーテの「親和力」である。二組の男女がそれぞれの連れ合いでない相手に惹かれ合うというメロドラマを物理学的な言葉を用いて文学に浄化させた作品だ。ありがち設定を芸術作品に仕上げるあたりが文豪だなぁと思ったものだ。というか、当時アメリカで流行り始めた言葉でいうと単に「スワッピング」なんだけど。
この関係は四人のうち誰か一人でも不満を感じたら、そこで終わり、という危ういものだった。そもそも一人が自分の妻(夫)を寝取られながらも、妻(夫)以外の人物と関係をもつことで「お互い様」という関係を成り立たせようという、無茶な話である。人間はそんなに公平には出来ていない。公平であろうと思っても、自分にとってメリットであることだけを残し、自分にとってマイナスな要因はできるだけ排除したいものだ。
彼らには子供がそれぞれ二人いる。子供を愛しているようでいて、誰もが子供のことよりも自分たちの欲望に忠実で、放っておいたり、一緒に食事をしなかったり、である。所詮「子供」であることを脱し切れてない中途半端な大人なのだ。
セイヴァリンとイーディスの二人の問題からこの関係は発生しているのだから、同じ問題に立ち返ったとき、四人の関係は崩壊する。崩壊後もウチはセイヴァリンを愛し続け、「僕」はそれが許せず、ウチの抱えている問題と取り組もうとせず、放っておくことで復讐しようとする。結果、「僕」からウチは去って行く。
「僕」にとってイーディスは魅力的な相手だったけれど、イーディスの方は「僕」に恋をしていたわけではなかったわけだから、実際、セイヴァリンとイーディスの二人に「してやられた」夫婦だっただけのこと、という結論が明らかになる。「僕」はイーディスとの情事に夢中になり、ウチのことを本当は考えていなかった。それはセイヴァリンにしても同じことで、ウチのことはろくに考えていなかった。だが、イーディスのためにこの関係を続けていたのだから、セイヴァリンとイーディスには修復の余地があるとも考えられる。
果たして、この「歴史小説家」は何かを学んだのか、それとも何も学ばなかったのか。ウチと彼は復縁できるのか?彼は未来に希望をもってウチを迎えに行くのだが、それは実を結ぶのだろうか?
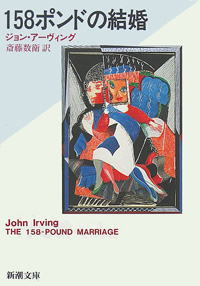 斎藤数衛訳 新潮社 新潮文庫 1990.8.25 560円 ISBN4-10-227305-0
斎藤数衛訳 新潮社 新潮文庫 1990.8.25 560円 ISBN4-10-227305-0
 ■マドレデウス Ainda / Madredeus
■マドレデウス Ainda / Madredeus