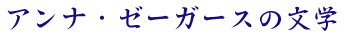Der Aufstand der Fischer von St. Barbara, 1928
聖バルバラの漁民一揆
大山定一訳 世界文学社(京都) 1946
道家忠道訳 「世界文学全集 21 ゼーガース・アンデルシュ・ノサック」集英社 1965.10.28
道家忠道訳 「筑摩世界文學大系 87 名作集II」筑摩書房 1975.8.25
聖バルバラの漁民の一揆は、過去四年の条件のまま、ただ出航を遅らすだけに終わった。フルがポルト・ゼバスチアンに護送され、アンドレアスが岩礁の間を逃走中死んでしまう前に、実は一揆はすでに終わったといってもよい。知事はこの入り江の治安が回復されたと首都に報告したのちに、この地を去った。聖バルバラはいまはほんとに、毎年の夏と変わらぬように見えた。しかし軍隊がすでに引きあげ、漁夫たちが洋上に出たのちも、一揆はなお、人気のない、白っぽい、夏の陽にさらされた広場にどっかりと腰をすえ、おのれが生み、育て、養った者たちのことを、そして彼らの最善のためにまもったことを、ゆっくりと思いつづけていた。
この冒頭の一文は不思議な力をもって私に迫って来る。
「一揆」という言葉が人格をもっているわけではないが、この文章の中では「主格」なのだ。主人公のフルやサブの重要な脇役アンドレアスさえも、本当に「一揆」の中でうごめく、一揆が生み出した子どもたちにすぎない気がしてくる。
フルは捕まるから逃げろという漁民たちの声、自身の内心の声に逆らい、いつまでも聖バルバラに居続け、兵隊の手から間一髪で逃れたにもかかわらず、また舞い戻って来る。アンドレアスは街を離れ航海に出たいのに、そのチャンスを一揆のために自らつぶして追われる身となる。ケデネクでさえ、発砲されることがわかっていて、一人、兵士の前に歩み出る。
それがすべて個々人が自分の意志で決定していることなのだが、一方で「一揆」という主人公が、彼らが自分を越えた何かを成し遂げようとすることに対して、後押しをしているようにも読みとれるのだ。
この作品はゼーガースの第二作目であり、荒削りな、ストイックな文面が目立つ。まさに「革命」を描いた作品ではあるが、いわゆる社会主義リアリズムをもって描かれる革命文学とは一線を画しているように見える。悲壮感や甘さのかけらもなく、短い文章で革命を描ききっているからかもしれない。
全編に描かれる風景は暗い。寒さと雨とフルの語る海の向こうの世界はアンドレアスにとって一瞬希望のような輝きをもって見えるのだが、具体的には何も語られていない。貧しさと飢えが、骨張った頬や薄い肩など登場人物の体格の描写にひしひしと感じられる。
にもかかわらず、作品は明るい力強さに満ちている。作品の冒頭で、フルは死の予感に襲われる。ケデネクも死の直前にその予感に襲われるが、彼らに悲壮感はない。特にアンドレアスの最後で繰り返される言葉は「もっと先へ」。死してなお、さらに先へ向かおうとする力が感じられる。一揆は何に結果ももたらさずに終わったが、この後の前進を暗示して、幕を閉じる。
それにしても、懐かしい。大昔、原文で必死で読んだが、冒頭の一文だけが、今でも忘れられずに頭に残っている。細かなことは忘れていたが、読むと一つ一つの言葉がどんな意味をもっていたのか、ほかの作品より手のとどくところに言葉があって、すぐにつかまえられるような気がしてくる。
苦学の甲斐が多少はあったか。。。
2001.9.25