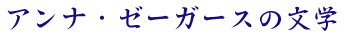Der Ausflug der toten Mädchen, 1946
死んだ少女たちの遠足

上小沢敏博訳 朝日出版社 1964.10.15 p1~64

長橋芙美子訳 「世界文学全集 94 ゼーガース/A.ツヴァイク/ブレヒト」講談社 1976 840円
宇多五郎訳 「戦争が終わった時―戦後ドイツ短篇15人集」桂書房 1968(死んだ娘たちの遠足)
亡命先のメキシコで書かれた作品。自伝的な要素の少ない作家だが、めずらしく本名の「ネティ」として登場する。ネティ自身が作品の語り手となっているため、実話であるかのような錯覚が起きてしまう。
メキシコへ亡命してきたネティがある日白い壁の向こう側で見たのは、女学生の頃仲良しだったマリアンネとレーニーがシーソーにのっている姿だった。それはまだ第一次大戦も始まっていない時代、先生やクラスの生徒たちがライン川を船で下る遠足に来ていたのだった。
純粋な友情によって結びつけられたように見えるマリアンヌとレーニーだが、後にレーニの夫が反ナチ活動で逮捕され、その子供を逃がすための旅費を工面することを、マリアンネはひどい言葉できっぱりと断ることになる。マリアンネの夫がナチの高級将校だったからである。
先生と仲の良い生徒だったが、後にその先生を「ユダヤ人座るべからず」と書かれたベンチに座っていたために、ひどい言葉で追い払ってしまう者もいる。夫が鉤十字の旗を部屋から垂らしたために自殺してしまう者もいる。それぞれの悲惨な運命を辿ることになる少女たちが、この日は穏やかで楽しい遠足の一日を過ごしている。
遠足を終えた少女たちは船でマインツの船着き場に到着する。ネティは家の前に帰って来たが、窓から姿を見せた母親のいる家の中にどうしてもたどりつけない。そして、メキシコのもといた場所に戻って来てしまう。
ネティは先生に「旅が好きで作文が上手だから、今日のことを作文にしなさい。」と言われたことを思い出し、この短篇を書くのであった。
1930年代後半からのゼーガースの作品は非常に映画的で、流れるように移り変わる情景が、読者の想像の中にわき起こるような作風になっている。過去のフラッシュバックが入りながら、美しい遠足の風景が描かれている映画を見ているような気になる。
命からがら逃げてきたメキシコで、故国への募る郷愁を押さえきれずに書かれたような、そんな作品である。
2001.10.10
Post ins gelobte Land
約束の地への手紙
河野富士夫, 松本ヒロ子, 貫橋宣夫, 河野正子訳 「グルーベチュ―アンナ・ゼーガース作品集」 同学社 1996.10.1 ISBN4-8102-0096-5 2,500円 261p
1946年『死んだ少女たちの遠足』がニューヨークで発表された。書かれたのはメキシコ亡命中の1942年~1943年である。ちょうどパリを脱出し、あちこちを経てメキシコへたどり着いた体験がこの作品の中に生かされている。
1890年代にポーランドの「L」という街でコサック兵によるポグロム(ユダヤ人虐殺)が起こり、ここでグリューンバウム家の息子たちが殺され、そのショックで次女が死んでしまう。次女の娘婿のナータン・レヴィとその幼い息子ジャック、父母は長女の嫁ぎ先を頼って、まずウィーンへ、それからカトヴィッツ、最後にパリへ移り住む。
一家は、亡命者たちの集まるパリの一角に故郷の町のような住み心地の良さを感じ、そこに落ち着く。そこでレヴィの息子ジャックが成長し、ユダヤ教ではなく、フランス革命の精神を感じて成長し、第一次大戦では出征する。戦後、眼科医の勉強を始めたジャックは名医となり、隣に住むソルボンヌへ通う女学生と結婚し、幸せに暮らしている。
ところが、年老いたレヴィは「約束の地」パレスチナの老人ホームへ永住することを息子達に告げ、定期的に手紙を送ることを約束させて旅立っていく。ジャックは約束通りレヴィに手紙を送るが、そのうち自分が不治の病であることに気づいて、死後も定期的に手紙を送れるよう、大量に書き続ける。
ジャックの死後、妻は夫の遺志を継いで手紙を送る。第二次世界大戦が始まり、パリがナチに占領されそうになると、フランスを脱出しようとするが、病弱な息子のために間に合わない。手紙は先にアルジェに逃れる知人に預け、ちょうど老人の死の直前にはかったかのように最後の手紙が届く。その後もアルジェに逃げた知人は老人の元へそっくりの手紙を送るが、受取人はいなかった。
静かな感動を呼び起こす作品である。死ぬまでに「約束の地」へ行きたいと願い、願い通りパレスチナへ行くが、まず息子たちのいる「パリ」に故郷を感じ憧れ、その後「ただ恥辱と苦悩しか体験することのなかった」生まれ故郷・ポーランドへ憧れを感じる。作者自身ユダヤ人としての流転の苦労を味わい、「喪失された故郷」が果たしてどこなのか、それを形作るのは何なのか、が作品の中に書かれている。それは共に過ごす「家族」、身近にあって気づかぬ「自然」、そして「日常」である。
主役はジャックの書く手紙である。先に起こることが予想できない分、その手紙は家と患者のいる医院との往復である、「日常」の繰り返しが描かれることになる。それがかえって非常に力強く感じられ、読む者の胸を打つ。
19世紀末~第二次大戦までのユダヤ人の体験が描かれた作品、と聞くと暗く悲惨な作品をイメージしがちだが、まったくそんなことはなく、特にパリへ来てからの生活や息子の成長ぶりに力強さが感じられ、さらに作者のユダヤ人一家へのあたたかいまなざしもあって、とても優しい作品となっている。
2001.9.30
Die Saboteure, 1946
サボタージュの仲間

長橋芙美子訳 「世界文学全集 94 ゼーガース/A.ツヴァイク/ブレヒト」講談社 1976 840円
「第七の十字架」その後、のお話。対ロシア戦開始直前の頃になっている。ゲオルグ・ハイスラーを助けたヘルマンとハイスラーの行方を必死で追っていたフランツ・マルネが主な登場人物である。フランツは物語の終盤で出会ったロッテと結婚している。
ヘルマンとフランツはかつて無二の親友だったが、今はつまらないことで仲違いして絶交状態にある。ヘルマンにはパウルという友人がいる。工場は手榴弾の兵器工場となっていて、対露戦が開始されるのを聞き、驚愕した労働者たちの中からサボタージュの動きが始まる。きっかけはヘルマンとフランツ、そしてパウルだった。それを検査係のクルスは気づいて気づかぬふりをした。
不発弾の不良品が相次いだことから、ナチは原因を追及し、突き止める。ヘルマンは連行され、処刑されるが、フランツとパウルはとっくに召還されていた。
根強い反ナチの思いが、戦時下のドイツでも息づいていた、という物語。
ヘルマンとフランツの仲違いはいざという時のための見せかけの絶交だったとヘルマンのマリーは気づいている。ヘルマンはずっと心の奥底で反ナチの強い意志をもったまま生きていることをマリーは理解していた。頭が弱いと思われていたマリーだが、自分が何も気づいてないとヘルマンに信じ込ませることが、ヘルマンの心の安らぎであることを知っていた。
孤立した労働者たちがサボタージュによって一瞬の間だけ結ばれる。そして再びバラバラになる。戦後、また彼らは結びつく。死者になった者、戦場から帰って来た者。死者の妻たちの強い結びつきもある。
ゼーガースは瓦解した世界で生きようとするドイツ民衆の未来を祈るような気持ちで書かれたに違いない。戦場から帰って来たシュペングラーの姿、マリーの姿にそれが見える。
かれはここ数年間に爆撃で破壊された都市をいくつもとおりすぎてきていたが、いいまここで、自分が生れたときから輝いていたふたつの星座が消えてしまったかのような気がした。ただライン河だけが爆破された橋をとおってかわりなく流れている。塔や城壁のぎざぎざの緑を映そうと、瓦礫と石塊の混乱した境目をうつそうとかわりなかった。
2001.10.14